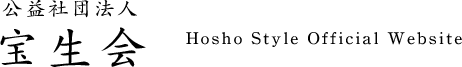
十一月 宝生会定期公演
◇午前の部◇2025年11月15日(土)11時始
能「井筒」
在原寺の跡を訪れた僧の前に一人の女が現れます。水を汲み、花を手向ける女に不審を抱いた僧は言葉をかけ、業平に所縁のある人かと尋ねます。女は生きている時から昔男と言われていた業平に何の所縁がありましょうと答えますが、紀有常の娘と業平の恋物語を語り、紀有常の娘の霊であることを仄めかして井筒の陰に消えてしまいます。その夜、僧の夢に業平の姿で現れた女は、美しい舞を舞い、井筒を覗き込み、そこに恋しい業平の姿を見て、夜の明けると共に去って行きます。世阿弥作にして能を代表する屈指の名曲です。「物着」(ものぎ)という小書がつくと、シテは中入せず後見座で装束を着替え、間狂言がなくなり型もかわります。
シテ 小倉伸二郎
能「熊坂」
美濃の国赤坂辺を通り掛った僧は、ある者を弔って欲しいという僧に呼び止められます。僧が乞われるまま庵室に行くと仏像などはなく、長刀や兵具がたくさんあり、不審に思い尋ねると、この辺りは山賊や夜盗が多く、襲われる人がいたなら助けに行くのだと言います。語る内いつしか相手の僧も消えて、庵室も無く自分も草叢に臥せっていたのでした。僧が弔っていると夜半に大盗賊熊坂長範の霊が現れ、牛若に討たれた有様を仕方話に語ります。小書「床几之形」は、常は床几から立ち上がって舞い始める型を、床几に掛けたまま舞います。
シテ 土屋周子
狂言「痩松」
ふところ具合のわるい男。山中で袋を背負った女と出会い、長刀で威して袋を奪い、包んである小袖や化粧道具を家の土産にしようとするが、油断しているところを先程の女に逆に威され、袋を取り返されてしまいます。
◆午後の部◆2025年11月15日(土)15時半始
能「玉葛」
長谷寺に参詣する僧が初瀬にさしかかると、川舟を操る女性が通りかかります。女は、僧を二本杉に案内し、源氏物語の中で、玉葛が母の夕顔の死後、九州に下って乳母に育てられていたが、都に上ってこの二本杉で母の侍女であった右近に会い、光源氏に引き取られることとなった事を語ります。そして自分こそ玉葛の霊と名乗り、弔いを頼んで消え失せます。後半、弔いの内に玉葛は狂乱の体で現れ、我が身に降りかかった男たちの妄執の苦しさをを語ります。
シテ 金森良充
能「絃上」
琵琶の名手藤原師長は日本にはもう学ぶべき師がいないと思い唐に渡る為、須磨の浦に立ち寄ります。一夜を求めた老人夫婦の所望に任せて琵琶を弾きますが折からの村雨に途中で止めてしまいます。琵琶と雨の調子の違いを言い当てた翁に、師長が強いて琵琶を弾かせると見事に弾きこなし、我こそ名器「絃上」の主、村上天皇の霊であると言って消え失せます。夜半生前の姿で現れた天皇は舞を舞い、竜神に「獅子丸」を持参させ師長に弾かせます。「クツロギ」という小書では、後シテの舞う「早舞」の途中にシテが橋掛りへ行く型を見せます。
シテ 佐野登
狂言「成上り」
清水寺に主人と参篭する太郎冠者。居眠り中に主人から預かった太刀をすっぱに青竹とすり換えられてしまいます。翌朝驚いた冠者は、一策を案じて、帰る途中に成り上りという話をはじめ、お預かりしたお太刀はこのように青竹に成り上がりましたと主人に差し出しますが…。



