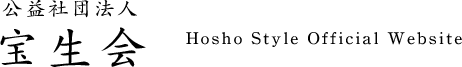
演目解説・演者紹介
◇午前の部◇
阿蘇の宮の神主は都に行く途中、高砂の浦で松の木陰を清める老夫婦に出会います。二人は神主に問われるまま、古今集の序に書かれている相生の松の謂われや、万葉集などを引いて松のめでたき事を語り、実は相生の松の精であると明かし、住吉にて待つと言って去って行きます。
神主は折から新船の乗り初めを勧める船頭の船に乗り、高砂の浦から住吉へ渡ると住吉明神が現れ、颯爽と舞を舞います。
長寿の象徴として松のめでたさを主題に置く神能の代表曲にして、誰もが知る有名な能です。

帝の霊夢によって剣を打つ事を命ぜられた三条小鍛冶宗近は、自分に比肩する程の相槌がいないことに困り、氏神である稲荷明神に詣でます。そこに現れた童子は、帝から宗近に勅諚があったことを既に知っており、名剣の謂われを語って宗近を励まし、剣を打つ台を用意して待て、必ず助力のために参上すると約束して去ります。
宗近が待っていると稲荷明神が神狐となって現れ、協力して剣を打ち上げます。

◆午後の部◆
一ノ谷の合戦で敗れ、源氏方に捕らわれた平重衡は、狩野介宗茂のところで処刑を待つ身でした。頼朝のはからいで遣わされた千手という遊女は、重衡を慰めるため連日伺候し、琵琶や琴を持参して重衡の相手をしていました。宗茂も重衡を大切にいたわり、酒を持ちて三人の雨中の酒宴が始まります。
朗詠を口ずさみ、千手が舞を舞っていつしか明け方も近くなり、琴を枕の短夜が明けると、刑場に旅立つ重衡を、千手は泣く泣く見送るのでした。儚い一夜の物語。

最明寺時頼は旅の僧に身をやつして諸国を巡っていました。摂津の芦屋で一夜の宿を借り、月若という前領主の子が伯父の藤栄に領地を奪われ、零落している事を聞き、家の者から重書を預かると、次の日一緒に藤栄の領地に出掛けます。
鳴尾の何某と浦遊びに興じ、酒を飲み、舞を舞ったりしている藤栄に声を掛けると、八撥を所望します。藤栄が舞の最後に僧に詰め寄ると時頼は正体を明かして藤栄を懲らしめ、月若の本領を安堵します。

狂言「鐘の音」(かねのね)
主人は成人した息子に黄金(こがね)造(づく)りの太刀を作ってやろうと、太郎冠者に鎌倉へ行って「金(かね)の値(ね)」を聞いてこいと命じます。太郎冠者はこれを「鐘の音(ね)」と勘違いして、鎌倉の寺々をめぐり歩き、鐘楼堂の鐘をついて音色を聞き比べて帰宅します。さっそく主人に報告すると……。それぞれの鐘の音は演者が口で言い、その擬音語は巧みで様々に工夫されています。
狂言「文山賊」(ふみやまだち)
二人の山賊(山の中で人や家を襲う盗賊)が武器の弓矢と槍を持って旅人を追ってきますが、山賊の一人が「やれ、やれ」と言ったのを、もう一人は「遣れ(逃がせ)」だと勘違いし、獲物を逃がしてしまいます。二人は言い争いとなり、果し合いをすることになりますが、見物人も無く誰にも知られずに死ぬのは残念だからと書置きを残すことにしました。書き上げた後、その文章を読み始めた二人は……。
◇午前の部◇
周の穆王の時代の都、人々が平和な御代をたたえている時に、桃の枝を肩にした美しい女が皇帝の前に現れます。女は、これは三千年に一度だけ花咲き実生る桃で、今めでたいこの御代にこそ誠に相応しい物と皇帝に捧げ、我が身は西王母の分身であると名乗り、今度は桃の実を捧げましょうと去って行きます。その後、侍女に桃の実を持たせた西王母が現れ、皇帝にその桃の実を捧げ、美しい舞を舞います。

行方知れずになったわが子を訪ね、諸国をめぐる僧が清水寺を訪れます。そこで人々に人気の「花月」という少年に会います。少年は都に流行の小歌を歌い、手にした弓矢で鶯を狙いますが、人々に殺生戒を思い出させて弓矢を捨て、更に清水寺の縁起を仕方話に舞って見せます。
その様子を見ていた僧はこの花月少年こそ我が子だと気付き声を掛けます。寺の男はびっくりしますが、顔が似ていると納得して名残りに鞨鼓を所望し、花月は鞨鼓の後に、天狗にさらわれ山々を巡った様を舞って見せ、僧と一緒に帰って行きます。

◆午後の部◆
木曽からやって来た僧は粟津ヶ原で女に出会います。僧が声をかけると、女は僧が木曽から来たことを知り、ここは木曽義仲が最後に自害した場所なので、祀られている義仲に一緒に手を合わせて欲しいと頼みます。夕暮れが近づき、僧に感謝しつつ女は去って行きますが、夜になり、今度は甲冑姿で長刀を手に現れます。女は巴御前の霊と名乗り、義仲の最後と自分の戦いを見せ、義仲の命令で木曽に戻らねばならなかった恨みを述べます。

春の大原山に花を見に来た男は桜の枝を掲げた風流な老人に会います。老人は昔を思い出して大原山の桜を愛で、神代のことが思い出されるとつぶやきます。男は不審に思いその事を尋ねると、老人は昔二条の后が大原山に花見に訪れた際、同行していた在原業平が、后に秘めたる恋心を神代の事として歌を詠んだ事などを語り、夕暮れ時になってその姿は人ごみに紛れて消え失せてしまいます。その夜ありし日の業平が優雅な姿で現れ、花の下で典雅な舞を舞います。

都での訴訟も無事に済み国許に帰ることになった大名は、日ごろ信仰する薬師如来のご利益であろうと、太郎冠者を連れて因幡堂へ参詣に行きます。国許でも堂を建てる際の参考にしようと、二人で堂のあちこちを見ているうちに、鬼瓦が大名の目に留まります。その鬼瓦が誰かに似ていると言いだした大名は……。
大名が供を連れずに北野のお手水(ちょうず)(御手洗(みたらし)祭)へ向かう途中、供になるような人が通りかかるのを待っていると、若狭の小浜の昆布売がやって来たので、同道しようと声をかけます。大名は昆布売に無理やり自分の太刀を持たせ、気分良く従者のように扱っていましたが、そのうち腹を立てた昆布売は……。昆布の売り声は謡節や浄瑠璃節など様々な節で謡われます。
◇午前の部◇
桓武天皇の臣下が大宮造営中の伏見に赴くと、人々に交じって神主姿の老翁が現れ、言葉を交わしていると、天より金札が降って来るという奇瑞が起きます。臣下が金札に書かれた文字を高らかに読み上げると、老翁は伏見の謂れを語り、天津太玉の神とは我なりと名乗って宮に入ります。
金札を頭上に戴き、あらためて神の姿で現れた天津太玉の神は、弓矢で悪魔を祓い、弓弦を外して太平の御世を寿ぎます。

長閑な春の三保の松原。漁師白竜は、松の枝に美しい衣を見つけ持ち帰ろうとしますが、世にも美しい女が「それは私の物ですから返して下さい」と呼びとめます。白竜は衣の主が天女であることを知ると、もっと頑なになり返そうとしません。
天に帰れなくなった、と天女があまりにも悲しむのを見て、舞を見せてくれるなら返そうと言います。舞うためには衣がいるという天女の言葉を一旦は疑う白竜でしたが、天には偽りはないと言われ衣を返します。
小書「盤渉」は常の「序ノ舞」が途中から一調子高い「盤渉調」になり、型も変わり、最後にシテはそのまま幕に入り、ワキが見送って留めます。

◆午後の部◆
京都西行庵の西行のもとに花見の都人達がやって来ます。花も一木、我も一人と静かな花見を楽しんでいた西行でしたが、はるばる出掛けて来たのだからと都人達を招き入れます。
暫くは同席していた西行が思わず、これも桜の咎でもあろうかと詠吟すると、古木の内より老体の桜の精が現れ、歌の真意を質し、桜の咎とは何か、ただ花を咲かせるだけの桜に罪はないのではと言い、舞を舞い、明け方の闇に去って行きます。

陸奥への旅の途中、立山禅定のために立ち寄った僧は、異様な雰囲気を持つ老人に呼び止められ、陸奥外の浜にある漁師の家への伝言を頼まれます。証拠も無しに訪ねてもと、訝る僧に老人はその時着ていた衣の片袖を取って与えます。
僧が外の浜を訪ねて行くと一年程前に死んだ漁師の家があり、衣も確かめられたので、約束通り供養をすると、死んだ漁師の霊が妻子の前に現れ、殺生の罪で苦しむ様を見せ、助けたまえと言って去って行きます。

狂言「悪坊」(あくぼう)
西近江から東近江へと帰る出家が、悪酔いした悪坊に絡まれます。悪坊は長刀で出家を脅しながら茶屋へと連れ込むと、腰を揉ませて寝入ってしまいます。その隙を見て逃げ出そうとする出家は、ぐっすり眠っている悪坊の小袖や長刀を取り上げ、代わりに自分の僧衣や傘を置いてゆきます。やがて目覚めた悪坊は、身辺の様子がすっかり変わっているのに気づき…
狂言「二人大名」(ふたりだいみょう)
春の良き日和に連れ立って野へ出かけた二人の大名。召使を連れずに来たので、通りがかりの者を無理やり従者に仕立て、嫌がるのも聞かずに脅して太刀を持たせます。散々な目に遭わされた通りの者ですが、太刀を持っては形勢逆転。今度は通りの者が大名を脅して、脇差や小袖裃を取り上げるだけでは飽き足らず、これを返して欲しければと二人を嬲るのですが…