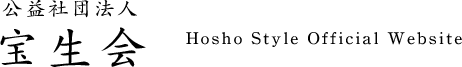
七月 宝生会定期公演
◇午前の部◇2025年7月19日(土)11時始
能「枕慈童」
魏の文帝に仕える臣下が、勅命により薬の水の源を尋ねて山中へ分け入ると、菊の咲き乱れる場所で不思議な慈童に出会います。臣下が訝しく思いその存在を疑うと、慈童は周の穆王に仕えたといい、それは八百年も昔のことなので、さらに疑われてしまいます。慈童はこの山に放逐されたとき、法華経の二句の偈を書き添えられた枕を賜っており、この妙文を菊の葉に写してその露の水を飲んで不老不死となったことを告げ、長寿をもたらした枕を讃え、帝に祝福の言葉を捧げて舞を舞います。
シテ 上野能寛
能「通盛」
阿波の鳴門で平家一門を弔う為、夜の読経を続ける僧の前に、篝火を焚いた舟が現れます。その舟には若い女と老人が乗っていました。僧が声を掛け、篝火ごと舟を岸に寄せて欲しいと頼むと、老人は舟を寄せ、僧の求めに応じて平家一門の最期を語ります。中でも平通盛と小宰相局について二人で身の上のように語り、入水すると見せて姿を消してしまいます。僧が回向すると通盛と小宰相の霊が現れ、二人で最後の別れを惜しんだこと、木村源五重章と戦って相果てたことを語って回向に感謝して去って行きます。
シテ 朝倉俊樹
狂言「苞山伏」
薪を取りに行くため朝早く家を出た山人は、眠くなり道で寝ることにします。そこへ修行中の山伏もやって来て、長旅で疲れたため山人の近くで横になり寝ていると、用事があって使いに出た男が通りかかります。男は、山人が昼食用に持っていた苞(藁でつつまれた弁当)を見つけ盗み食いをしますが、山人が起きそうになると……。
◆午後の部◆2025年7月19日(土)15時半始
能「橋弁慶」
武蔵坊弁慶は、北野神社へ丑の刻詣(ときもうで)に出ようと従者に共を命じますが、従者は神社への通り道の五条の橋に、最近十二、三ばかりの小男がいて、通行人に悪さをすると聞いたので止めた方がいいと言って引き留めます。しかし弁慶は、それならばかえって退治してくれようと薙刀(なぎなた)をかついで五条の橋へ出向き、その少年との打合いに臨みます。さすがの弁慶もこの小男が牛若丸とは知らず、散々に翻弄され、降参して家来なることを誓います。義経と弁慶、二人の運命的な出会いを描きます。
シテ 當山淳司
能「錦木」
旅の僧が陸奥の狭布の里に着くと、若い男女に会います。二人は巾を狭く織った布の謂れと、美しく飾った錦木というものを、女の家ノ前に立てる事がこの里の求愛の風習である事と語り、女が受け入れず錦木をそのままにしたので、三年もの間錦木を立て続けた男の話をし、錦塚に僧を案内すると消えてしまいます。僧が弔っていると二人が亡霊となって現れ、錦木を立て続けて死んだ男がその妄執を訴え、夜明けと共に去って行きます。
シテ 武田孝史
狂言「酢薑」
津の国の薑(古くは山椒のこと)売りが都に上り商売をしようとすると、和泉の堺の酢売りがやって来て、目の前で酢を売り始めます。互いに系図を言い自慢し合いますがどちらも譲らず、それぞれの商売物「カラい」「スっぱい」によそえ、秀句(しゃれ)で勝負することにします。ところが秀句を言い合っては二人で笑いあい、いつまでたっても埒があかないので……。



